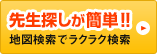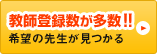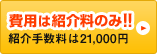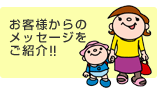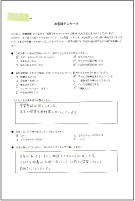基本情報

| 教師ID | 28754 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2017-05-17 ( 2017-05-17 ) |
| 住所 | 広島県三原市宗郷 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 31 歳 |
| 大学 | 日本文理大学 科目等履修生学部 - |
| 登録時の学年 | 1年 |
| 文理 | 文系 |
| 中学受験経験 | 無 |
| 出身中学 | 三原市立第3中学校 |
| 出身高校 | 広島私立桜が丘高等学校 |
指導経験
| 家庭教師経験 | 未経験(未経験) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 未経験 |
交通手段
| 交通手段 | 自動車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 三原駅 |
| 最寄りのバス停 | 田野浦小学校前 |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
| ○ | ○ | ||||||||
人物
| 自己PR | 私は、3年間、大分県警察本部少年課が展開する少年警察ボランティア活動に於いて大学生サポーターを委嘱されました。そして、その活動を通じて、非行少年の健全育成と彼らの居場所づくりに取り組み、様々な問題を抱える子供たちと真剣に向き合ってきました。 彼らの抱える問題は多岐に亘っており、その多くは劣悪な家庭環境に起因するものでした。 中でも「虐待」や「いじめ」と言った問題は一種の社会病と言えるほど複雑化、普遍化しており、国家的な取り組みが急務であるとすら感じました。 中でも彼らが抱える「心」の問題は特に深刻で、殆どの子供たちが一度や二度の面談では固く閉ざした心の殻の中から出て来てはくれませんでした。 その時に感じたのが「真摯に人の可能性を信じる」ということの大切さでした。体温を感じさせない「上辺だけの優しい言葉」は決して彼らの心の奥底には届かないのです。 そこで、私たち大学生ボランティアは根気強く焦ることなく、彼らの可能性を只管(ひたすら)信じて話し掛け続けることにしました。すると、最初は周囲の全てを傷つけるハリネズミの棘のようだった彼らが少しずつ打ち解けてきて、自分自身の話をしてくれるようになったのです。そして、彼らの話の多くは耳を覆わんばかりの惨(むご)いものでした。 彼らの話を聴きながら、私はハッとしました。彼らの纏っているハリネズミの棘は内側に向けても同じように生えていたのです。心に傷を負った子供たちは周囲を傷つける事で自らの心の痛みを誤魔化そうとします。ところが、結果的には自らの心を更に深く傷つけていたのです。 非行に走る子供たちが抱える心の闇はドラマや小説のように熱血指導や甘い心構えでは決して対峙する事を許されない現代社会の宿痾(しゅくあ)なのです。 私はこれらの経験から、自らが目指そうとしている教師という立場の人間が担うべき責務に関して改めて問い直してみました。「教師と生徒では学校に対する関わり方、考え方が圧倒的に異なっているのではないか?」 教師にとって学校は職場であり、大人として過ごす人生の時間の多くを捧げる場であり、多くの教師が「人生の目標」として教師であること掲げているのに対して、学生にとっては多感な青春時代のほんの一部分でしかなく、大人への通過点の一つに過ぎないのです。 無論、子供たちにとって、将来の選択肢を充実したものするためには充実した教育を受ける事に重要な意味がありますから、学校自体を蔑にして良いという事にはなりません。 そこで、子供たちには学校が「自らが目指す人生の目標を達成するための大変重要な手段・行程である」ことを明確に認識させ、学生としての時間を有意義に過ごすことの意味を教えなければならないと思うに至りました。 その為には子供たちの持つ目的の多様性に対応した指導が肝要であり、生徒の目線の先に在るものを共に見つつも、それらを俯瞰視する事によって、彼らが身に付けるべき教養や技術を身に付けるに当たり適切な助言を与えねばならないと考えます。 また、子供たちは更なる社会のグローバル化にも対応する必要があるため、異なる社会的背景や価値観を持つ者同士のディベートに耐え得る柔軟且つ強(したた)かな人間性の涵養も極めて重要だと考えます。 その為には単に知識としての「社会科」では無く、“Two-way communication”を成立させる相互に複合的な関わり合いを持った情報体系としての理解を深める必要があります。そこで、授業では、「協同学習」の場面を取り入れ,教師への発問に対して小数のグループでの意見交換、学級全体の意見の共有により,異なる意見が収斂するプロセスを実体験させることで、知り覚えることだけではなく,考える学習にしたいと考えています。 |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | - |
| 指導経験・保有資格 | - |
| コメント | - |