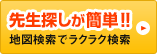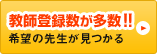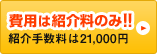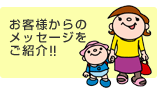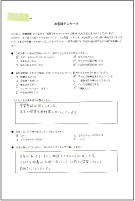基本情報

| 教師ID | 10747 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2012-01-04 ( 2013-06-01 ) |
| 住所 | 京都府京都市左京区上高野池ノ内町 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 40 歳 |
| 大学 | 京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科 グローバル地域研究専攻 |
| 登録時の学年 | 5年 |
| 文理 | 文系 |
| 中学受験経験 | 有 |
| 出身中学 | 東京学芸大学教育学部附属小金井中学校 |
| 出身高校 | 東京学芸大学教育学部附属高校合格 |
指導経験
| 家庭教師経験 | 2年(3人) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 未経験 |
交通手段
| 交通手段 | 自動車, 自転車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 国際会館 |
| 最寄りのバス停 | 上高野 |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
人物
| 自己PR | 趣味は読書、執筆活動、ドライブ、バイオリン、キャンプ、野球観戦等 地域研究の研究者を目指しています。 野球部を経て合唱サークルに所属していました。 現在はキャンプ団体に所属し、キャンプリーダー活動を行っています。 メンタルケアスペシャリストの資格を所持しており、対話による信頼関係の構築に活かせるかと存じます。 また、キャンプリーダーの資格も取得して長く、子ども達との関係作りの経験も多い環境にあります。 生徒さんと友人 のような関係を築きながら基本的に楽しく、時に共に苦しみながら勉強することをモットーとしております。 長期目標・短期目標をしっかりと定め、場合によっては自分で教材を作成するなど柔軟に指導してまいります。 私自身4度の受験経験がありますので、分かち合えることも多いかと存じます。 |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | 文系教科は全て得意です。また、中学までの理系科目も守備範囲です。 センターレベルであれば高校の理系科目も対応できます。 中学受験 私立海城中学校合格、国立東京学芸大学教育学部附属小金井中学校合格(進学) 高校受験 私立西武文理高校合格、国立東京学芸大学教育学部附属高校合格(進学) 大学受験 国立筑波大学第二学群比較文化学類合格(進学) 大学院受験 国立京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科合格 |
| 指導経験・保有資格 | 小学6年生受験指導半年(合格) 中学3年生受験指導1年(合格) 現在中学2年生軽度知的障害児担当2年目 メンタルケアスペシャリスト |
| コメント | 理念的な方針 私が家庭教師として最も重視していることは、生徒さんとの信頼関係の構築です。わかったところはわかった、わからないことはわからないと率直に言えるだけの関係性がなければ、そもそも家庭教師としての指導は成立しません。 それでは学校などの授業で内容がわからないまま聞き流しているのと同じです。 私は家庭教師が単なる「勉強を教える人」という装置になってしまっては、生徒さんとの信頼関係は築けないと考えています。 ですので、一人の人間として率直に向き合うこと、まずは自分自身をよく知ってもらうことを心がけています。そして、生徒さんのお話をよく聞き、共感し、一人の人間として尊重することを目指しています。 生徒さんの人生の貴重な時間の一部を預かるわけですから、これからの人生をよりよく歩んでほしいという思いで指導に当たるようにしています。 また、指導に当たっては指導方針を押し付けるのではなく、こちらの提案、見通しを伝えて選択肢を用意するなど生徒さんと話し合いながら双方合意の上で学習の進め方を決めていきます。 これも、お互いの信頼関係の構築の一翼を担いますし、生徒さんが主体的に学習に関わることのお手伝いにもなります。 実務的な方針 私の指導に関する考え方は3つあります。すなわち「知識の密輸入」「生活世界と学問世界の交流」「謎の発見」です。 「知識の密輸入」とは、すなわち教科を横断した知識の運用です。例えば歴史の学習で地学的知識を応用する(例:太陽の黒点の数で示される活動周期と日本の飢饉の周期との関係)、地理の学習で数学的知識を応用する(例:気温の逓減率の計算)といったことです。 得てして勉強は教科ごとの区分に縛られがちですが、それにとらわれずに柔軟に活用することで持っている知識を最大限に活用することができ、また、発想の幅が拡がります。 次に「生活世界と学問世界の交流」とは、とかく日常世界と切り離されがちな勉強の世界をうまく身近なものと繋ぎあわせていくことです。 自分の勉強していることが実際にはどのように社会で応用されているのかを学ぶということでもあります。 こうすることで勉強内容に更なる関心を持つことができます。 最後の「謎の発見」ですが、これは少々趣が異なります。 そもそも教科書や参考書に載っている事項というものは無限の自然界に比べればほんの氷山の一角に過ぎません。 既存の知識・理論は膨大な未解決の問題に比べればほんの些細なことなのです。 つまり、「教科書・参考書の内容=全ての答え」というわけではないのです。 私は、そのことを理解し教科書に載っていない未解決な問題に目を向けていくこと、究極には未解決の問題を発見することが知的好奇心の刺激につながると考えています。 「謎の発見」とはそういうことです。 以上、長文失礼致しました。 もし、私に興味を持たれましたらお声掛けいただければ幸甚です。 |